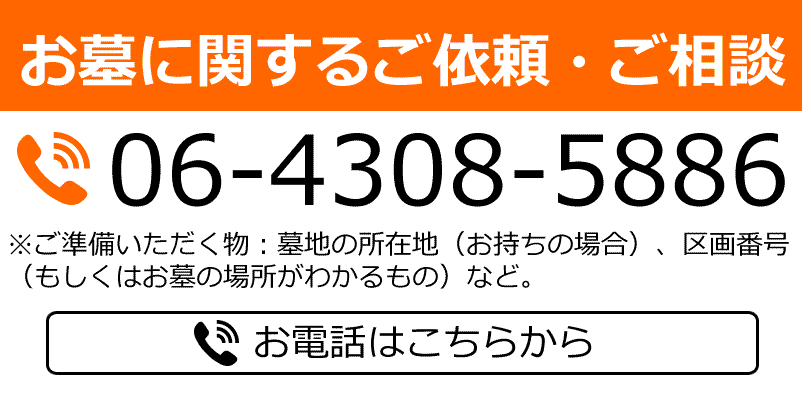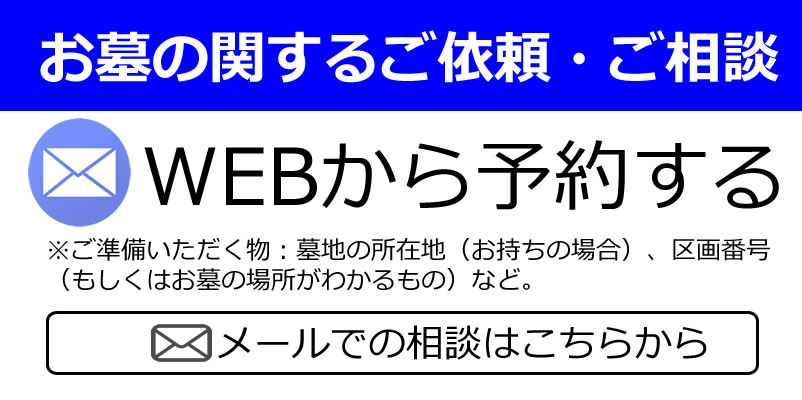墓じまい、墓石の撤去の工事や手続きの手順について一例を説明しています。
墓じまいの手順
一般的な手順になりますと墓地管理者の手続きからはじまります。その後は仏教徒の方は寺院の閉眼法要(魂抜き)の依頼をいたします。墓前にて拝んでいただきます。その後、撤去工事を行います。
手続きについて
墓じまいを行う前に、現在の墓所の「墓地返還届」手続きをおこないます。これは墓地管理者に対して行います。他に遺骨を取り出すための「改葬許可申請」も必要です。これは人数分の手続きが必要です。同時に墓石等の撤去工事の手続きをいたします。
改葬許可証の発行について
墓地管理者から人数分の改葬許可証を発行していただきます。よって5人分ですと5枚の申請書を提出いたします。これは遺骨の証明書として必要になってきます。次の新しいお墓に収めるときに提出いたします。永代供養のお墓はさまざまな所があります。自治体やお寺などが多くあります。その中で改葬許可証の提出が必要でないところもございます。しかし、ほとんどの所が必要になってまいります。
墓地の返還手続きについて
自治体管理のお墓の場合は「墓地使用許可証」などが必要になってきます。長年ご自宅で保管されているものです。しかし契約時以降は出すこともない為、紛失されている方も多くおられます。その際は、まず紛失届を提出していただきます。それにより墓地使用許可証の再発行をしていただきます。手続きには1週間ほどかかることもございますので早めの手続きがひつようです。
墓石等の撤去工事手続きについて
工事手続きに関しては当社ですることがほとんどですのでお客様がすることはございません。工事手続きに関しては上記の「改葬許可証」及び「墓地使用許可証」などの手続きが完了していことが必要になります。一部の自治体では当日にできることもありますが、やはり1週間ほどは余裕をもってすることになります。
閉眼法要(魂抜き)
仏教徒の方は寺院に依頼をいたします。拝んでいただく時間は10分~15分くらいになります。また宗教や導師により作法が異なりますのでご用意するものや時間なども違いはございます。
遺骨を取り出す
ご遺骨を取り出しますが、関西では晒し袋で納骨していることが多いのが現状です。ですから遺骨を取り出した時には、あらためて骨壺にいれるか晒し袋にお入れいたします。これは次のお墓まで持って行くために必要となります。骨壺は大きさも有る為、移動にかさばりますし重量もございます。ですから次のお墓が晒し袋で対応できる所でしたら移動は楽になります。
お墓の撤去作業
石碑や霊標板、巻石やベースなどその他の部材の残石残土を撤去し処分を行います。墓所は元の状態にキレイに更地状態に戻します。処分費は墓所の広さやお墓の大きさなどにより異なってきます。
まとめ
最後にご先祖様のご遺骨を移すには色々な手続きが必要になってきます。墓地の管理者により手続きの仕方が異なる場合がございます。手続きの代行もしています。寺院もご紹介しています。墓じまいのことならお気軽にご相談ください。