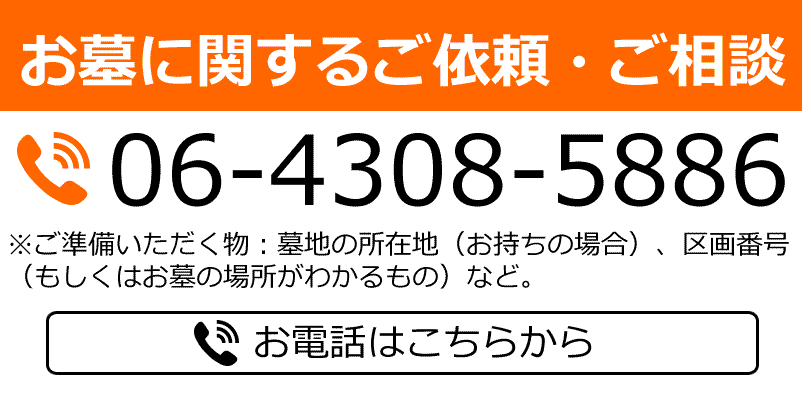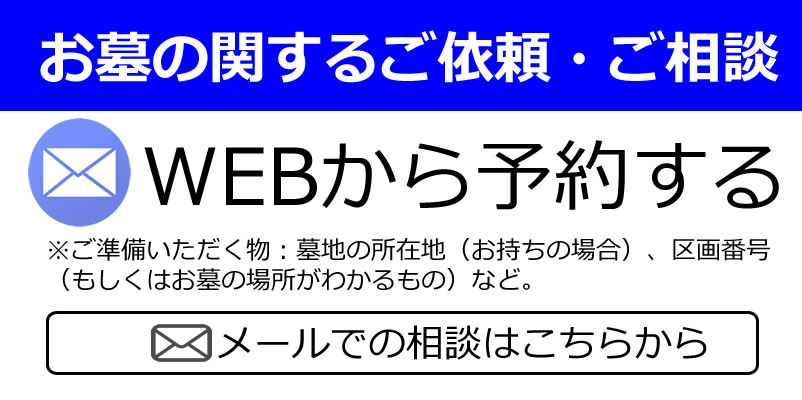人が亡くなられるとご家族とともに斎場に向かいます。そこで遺骨となります。そこでは骨壺は二つ用意されてかえってきます。大きい骨壺と小さい骨壺になります。なぜ二つに分けられているのでしょうか?これらを説明していきます。
小さい骨壺の納骨の仕方
地域により骨壺の大きさが違います。また選べることもあります。関西地域では骨壺を二つに分けられます。大きい骨壺は6寸程度の大きさです。小さい骨壺は喉仏がはいる大きさのものを使用します。それでは二つ渡されて、納骨の時にどうしたらいいのかお困りの方がでてきます。一緒にお墓にいれていいのか?どうしたらいいのかと思ってしまうのです。お墓には大きい骨壺を納骨します。それでは小さい骨壺はどうしたらいいのでしょうか?
2通りございます。一つは大きい骨壺と一緒にさらし袋にまとめてお墓に納骨いたします。もう一つの方法は他のお墓に納める方法です。それでは他のお墓ですが、これは例えば、お寺さんにある永代供養のお墓などに納めたりすることになります。昔から多いのはご自身の檀家寺のご本山に別に供養してもらうために納めることがあります。更に手厚く供養したいという考え方です。しかし、最近はほとんどの人がご一緒に納骨いたします。遺骨を二つに分けてかえってくるのは地域により異なります。
ご親族が亡くなられとやはり寂しいですね。その為、小さい骨壺をお仏壇にしばらく置いとかれる方もおられます。特にパートナーが亡くなると、やはり寂しいので自分が亡くなった時に一緒に入れてほしいと言われるかたもおられます。
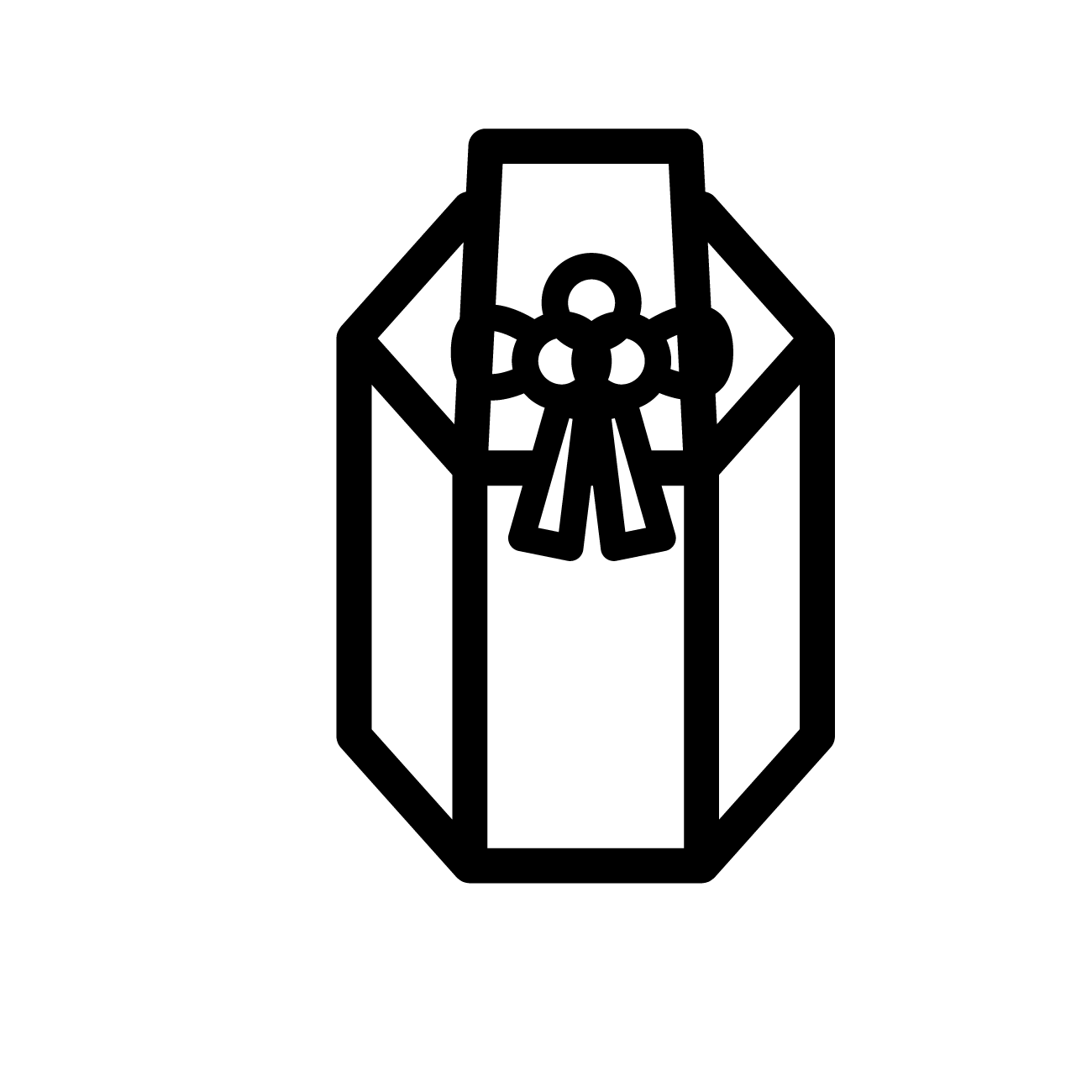
まとめ
骨壺は体の一部をお入れした物にすぎません。寂しさのあまりしばらく家に置いておきたいと思ってしまいますが、すでにお墓が有る方は土に還してあげるために良いタイミングで納骨してあげてください。故人様(先祖)にとりましても遺骨を見て泣かれているよりは、毎日元気に過ごしてほしいと思われるのではないでしょうか。納骨を済ませて元気な姿でお墓参りをしてあげることが一番のご供養となります。なるべく早めのご納骨をおすすめいたします。